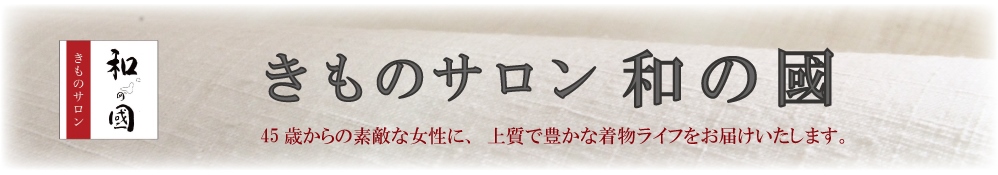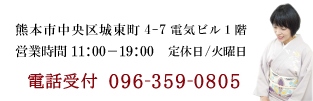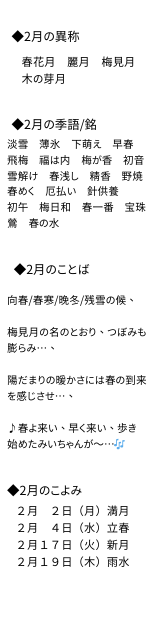今朝は、台所で父や母と暖かいお茶を飲み、会話を交わし、自宅(菊池)からの出勤となる。途中、上田和裁さんにも寄り、お仕立物を頂いてくる。結城紬と見間違えるようなのウール(崩し・栗茶・)を着て、肥後銀行上通り支店、11時。新任の担当者と打ち合わせ。僕は進化した。人目があまり気にならなくなっている。 お昼1時、八代のカトリック協会で告別式に参列する為、背中に「丸に剣片喰」のヌイ紋の入った鉄黒の御召(袖無双・単衣仕立)の上に、漆黒の結城紬(縮)羽織を着て、藍鉄色の博多織の帯を締め、グレーの足袋を履き車を走らせた。この冬初めて袖を通す「縮の結城紬」、求めたのは10年以上前だが、彼の居場所がやっと見つかったような感じだ。というのも、縮結城は元来、横糸に撚りをかけているので、結城紬に比べ肌に触れる面積が少ない。結城紬が砂のような手触りとすれば、縮結城は、小石みたいな凹凸感がある。元来単衣に最適な着物なのだが、「袷仕立もOK!」という、京都の仕入先の言葉を鵜呑みにしていた。袷仕立となると、胴裏が必要になる。男物の「絹の胴裏」や「上質の綿の胴裏」も使ってみた。「洗張り」をするたびに表生地は結城紬本物のもつツヤが出てくるのだか、ずっと着ていると、裏地にそぐわなく、袋が入ってくる。普段着として粗くきるからか、お仕立が悪いのか。ひと冬ひと冬悩みぬいた結果、「やっぱり縮結城は、袷仕立には向かない。」との結論を、僕は下した。 そして、「本当に黒々とした漆黒なので、羽織にすれば着物とも合わせやすいし、万が一、喪に服する時も着れる。」ということで、一昨年着物を羽織に作り変えた。「100万程する縮結城紬を、羽織に!」と思えば、高価かもしれない。しかし、自分で辿りついた境地のようなものだから、返ってその縮結城を羽織にすると、一生側にいてくれる。極端にいえば、冬寒い時は毎日毎日、その結城に触れることもでき、僕を暖かく守ってくれることにもなる。おかげ様で、4~5回「洗張り」しているので、より光沢も増し、しなやかでしっとりとしている。まさに、黒塗りの器に、摘草料理が優しく盛られいて、そこにダシがそそがれ、蓋を開けると、プーンと美味しそうな香りが漂ったような感じの羽織となっている。 さて、話を元に戻そう。大好きな羽織を羽織って「着物姿で、カトリックの告別式。」勉強になる。事前に、約束事を問い合わせていた。「不祝儀袋には、「ご霊前」でいいのか?」「何か特別な決まりごとはあるのか?」と・・・。讃美歌が鳴り響く中、白いカーネーションを献花する。最後は、故人のお櫃の蓋が開けられ、そこに献花し最後のお別れだ。僕は思った。僕が死んだら、お越しいただく参列者の方々が、庭先に咲いている野の花を献花して欲しい。ただそれだけでいい。そして服装は、喪服ではなく、僕がお勧めした着物を着てきて、「元気で行ってらっしゃい」と見送って欲しいと…。 午前中着ていたウールに着替え、「熊本ゆかりの染織作家展」出品者の溝口あけみ氏と、出品作品を目の前にしてお話ができた。今年、日本工芸会正会員になられただけの実力派。作品に優しさ、お人柄、そして芯の強さが表れている。熊本県伝統工芸館にも出向いた。someoriの吉田美保子氏よりも、お手紙が届いた。気がみなぎってくる。 夜7時からは、熊本県ハンガリー友好協会の郵便物発送。事務局としての務めだ。大学1年の娘もしっかり手伝ってくれた。ご褒美に「やきとり道場」に3人でいった。帰ってからPCを開くと、24節季の一つ「大雪」をテーマに送った「國さんメール」に対し、返信が数件きていた。僕は、とても嬉しかった。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】