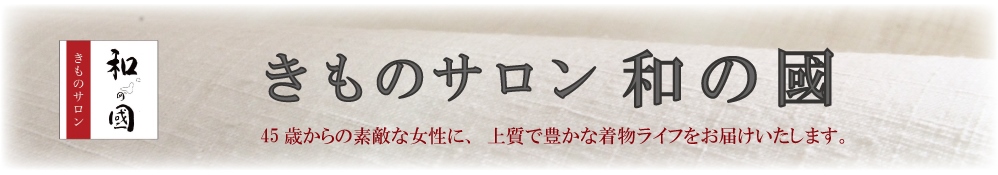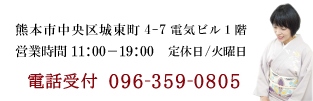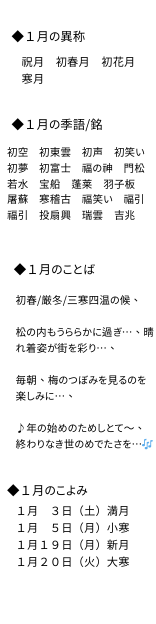菊池では「新宮さん」と呼ばれる秋の大祭が10月の13日~15日まで行われる。成人の日など日にちが変わる中、普遍の祭りがこの菊池の秋祭りだ。まさに、菊池精神。毎年その幕開けとなるのが13日。菊池松囃子能場で、御松囃子御能が披露される。夜明け前、菊池神社に向かって散歩をしていたら、能場が開いていた。扇は持ってないが、舞台に飛び乗り、こっそり「高砂」のお仕舞を小声でやった。目の前には、征西将軍・懐良親王御手植のものとも伝えられる樹齢600年の古木がデンと構えている。その将軍木を神様に見立てて舞えるとは有り難い。
私も、熊本市店(和の國)を出店する5年前までは、御松囃子御能保存会のメンバーで、囃子方の一人として参加していたので、様々な思いでが蘇ってくる。 また今日は「熊本白謡会」のお稽古日。東京から師匠の平戸仁英先生がお見えになるので、空港で出迎えた。その後店で「海士(玉の段)、敦盛、田村、高砂、清経、雲林院、猩々」などを吹き込んでもらった。謡をきいているだけで、颯爽とした気持ちになる。やはり五七五調のリズムの謡は素晴らしい。血流も良くなる気がする。お昼からは、パレアの和室でお稽古だ。この時期なのにまだ暑いのでサマーウール(濃紺・千筋)をきていた。袴を履きトンボの足袋から白足袋へと着替えた。心もシャンとする。私は、「高砂」の仕舞と「田村」のシテの謡。そしてそれぞれに、お仕舞や謡の稽古があった。非日常的だが、とても有り難い時間。着物が最高に似合う場所だ。 そして午後7時からは、NPO法人きもの普及協会の「人への着せつけの研修会」。今回はテーマが「男性のきもの」なので、男性が必要だ。家内に口説かれモデルとなったが、本当は男なら誰でも良いはずだ。心でブツブツ思いながらも、会が始まると本領発揮。いつも無意識に着物を着ているので、人へ着せてもらうことが、いかに着にくいかの人体実験をしているようなものだ。真剣に「締めすぎ。男のきものは上半身は特に楽に。決め手は角帯」など本音で言え、研修会も白熱してくる。私個人的に、「着物離れの三悪」と考えている「呉服屋・着物着付け教室・美容室」がより明確となった形だ。前の二つは、また折を見て触れるとして、その中でなぜ「美容室」が悪なのか?ズバリ。普段に着物を着ていない人が、成人式などで着物を着せるからだ。母が娘に着せるなら、娘が「腰ひもがきつい」と言えば緩めてくれるが、これが着付士となれば、「着物はきついのが当たり前だから辛抱しなさい」という。二十歳を祝うお振袖姿が、「あんなにきつい着物は絶対着ない」という着物離れの根幹をなしている。普段から、人ではなく着付けのボディに着せているのと、着崩れして美容室の名が落ちるのが不安だから余計に締めつける。見た目は美しいが、着せられた方は、たまったものではない。着せつけ人体実験をさせて頂いたので、こうやって自分が体感し本音を書けることがまた有り難い。 午後9時から、ピアニストの大ちゃんと一昨日の反省会を行った。いつの間にかオペラ等の西洋音楽も好きになり少し聞き分けが出来るようになったのは、20年近く謡を学んでいることと関連性が深い事に改めて気付いた。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】