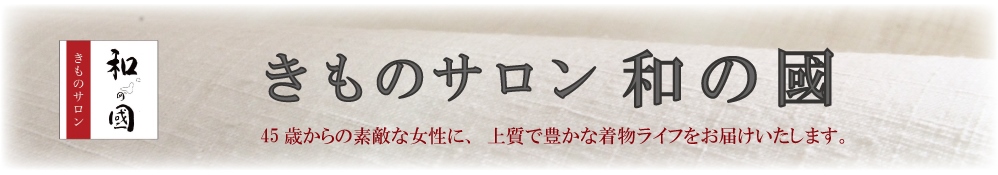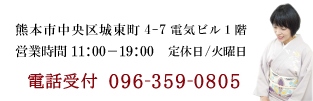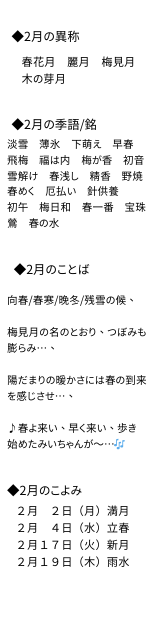社団法人茶道裏千家淡交会熊本支部の月釜が白川公園の茶室「海月庵」で行われている。柿渋染の紗の着物を着て、一席目に席入りし一腹頂戴した。贅沢な気分だ。店に戻り、スローライフを実践し和服をこよなく愛するご主人さまにご来店頂いた。時候の挨拶もままならぬまま、「着物談義」となった。そこで尋ねられたことが、「単衣と袷の着こなしの違いは?」「綿やウールなどは、どういった場所まで着ていいのか?」などだ。嬉しい質問に時の経つのも忘れるほどだ。「洋服を一枚も持たず、平成5年より着物を着続けたから言える言葉がある事」に改めて気づき、言葉を選びつつ、自己開示していった。 それから、氏は寒くなると暖をとるために「槇ストーブ」をたいているそうだ。聞くところによると、一時間に一度ストーブを明け、槇をくべるという。その折に熱風が右袖を襲い、着物の袖が危険地帯となるそうだ。良い知恵を探し出していたら、「タスキがけ」ならその心配もいらないということに気づいた。。早速腰紐を使い「たすき掛け」をやってみた。着流しの上に、たすきを掛けるのは何時ぶりだろうか?今まで業務をこなすうえで「袖がお荷物」になる場合、作務衣に着替えていたことが多かった。しかしながら「たすきを掛けて業務をする」という先人の知恵を生かし実践しようという…、また新たなる新鮮な気持ちが湧いてきた。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】