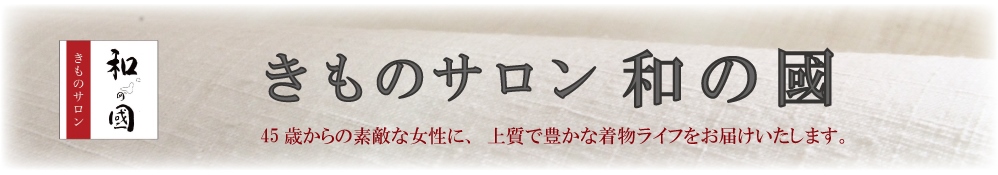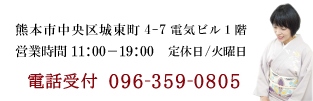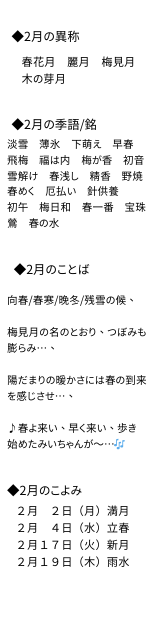今日は初夏の陽気に誘われ、今やこの季節の定番となっている片貝木綿に袖を通し、30年前、大学の入学祝いに両親に創ってもらった紬の袴をはいた。その当時は、グリーン色だったけれども、若干派手になって袴が目立ちすぎるので、「丸染め」という仕立て上がりまのまで色を濃めにする染色技法がある。その技法で緑の深い茶色(千歳茶)に染め上がったら、地色も着物を選ばず合わせやすく、生地風も体に馴染み、腰があるのに、肌触りも優しいというすぐれものの袴に変身してくれたので、今一番のお気に入りとなった。 洋服で言えば、まさに木綿のきものがジーンズだが、そこに袴を履いたのでジーンズにジャケットという、ややカジュアルスーツ的な装いとなりえる。そのように袴を履くだけで気持ちもしゃんし、着物の格も上がるが、午前中から袴を履いたのはもう一つの訳があった。 今日は、月に一度の「隆子ねーさんによる謡と仕舞いのお稽古日」。観世流のお仕舞いのお稽古で果敢にも「屋島」を学んでいるが、その動きには、きものでは裾がはだけて、その部分が気になってしまう。袴を履いて舞うと、裾さばきが全く違い、ダイナミックに動けるので、お仕舞いの為に袴は存在しえるのかと思ったりもする。袴が腰に当たるその感覚は、アルコール中毒ならぬ、袴中毒になりそうなほど、「頑張るぞ」という気の充実を図ってくれる。 夕刻は、片貝木綿+袴から、腰がある松坂木綿に着替え、紗の袖なし羽織を着て、「NPO法人きもの普及協会」設立の為、熊本県交流会館パレアに出かけた。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】