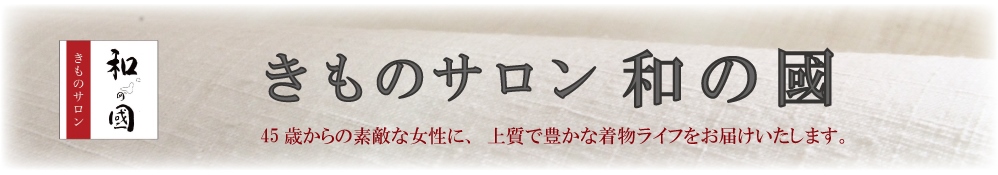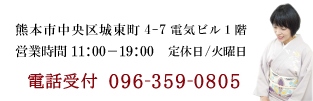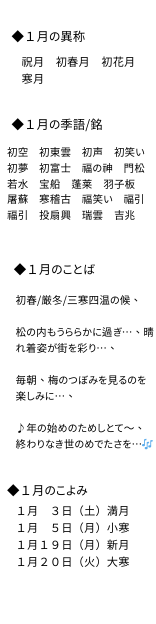昨日同様、麻の葉柄の鯉口に松坂木綿着て日常業務にあたった。帯も黄八丈だ。
紺色に辛子色のコーディネイトも好きだが、その帯を合わせたのはもう一つの理由がある。それは、来年2月に「染織家探訪の旅」と題し、東京都八丈島在住、染織界の巨匠・菊池洋守氏(八丈織)の工房を訪れる計画が進んでいるからだ。
今まで、沖縄の染織作家(平良敏子氏の芭蕉布、宮平初子氏の花織、玉那覇有公氏の紅型)、奄美の大島紬、天野圭氏の広瀬絣、徳島の藍染、群馬の芝崎重一氏(座ぐり)、長野県の横山俊一郎氏(みさまや紬)、茨城県の結城紬、青森県の裂織などを訪れた。しかし数回訪れたのは、結城紬だけだ。
一泊二日ではあるが、その旅が実現となると、一生に一度、最初で最後となる可能性が大きい。なぜならば、菊池洋守氏の年齢(70歳)ということに加え、後継者がない。いつまで織物を続けられるという保証もない。当方では、上記の染織家などを中心に年に一度計画しているが、再訪となるには10年程先になりそうだ。
国画会にも工芸会にも、どこにも所属しない、腕のみが命の孤高の染織家3人を「染織家三人衆(菊池洋守氏・芝崎重一氏・横山俊一郎氏)と称し我々は絶賛しているが、来年から実施する「染織家探訪の旅」の記念すべき第1回目に、一番行きたい所に行くことができるのは本当に夢のような話。現場を自分の眼で見れるというその喜びは、私にとってはクイーンエリザベス号に乗って世界一周の旅に出かけるのに匹敵する。
近江商人の言葉に、「三方良し」がある、。作り手もお客様もそして我々も皆良いという考えがある。この話を持ち込んだ折に、快諾くださった当方のメイン仕入先「室町の加納織物」の担当、加納荘五郎社長のおかげだ。また染織家の工房を訪れるとなると、その前後一週間は仕事の段取りも変わってるくるらしい。待つ側も見えない処でベストを尽くされる。全てが力を合わせ、新しいものが生まれてくる。 釈迦の教えに「六方拝」とある。「東西南北天地」の六方に感謝することだそうだ。いろんな方々のおかげで今があり、今日もまた着物を着て仕事をさせていただくことが出来る。本当にありがたい。八丈島のカリヤスで染められ黄金色に輝く角帯が、様々な思いを巡らしてくれた。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】