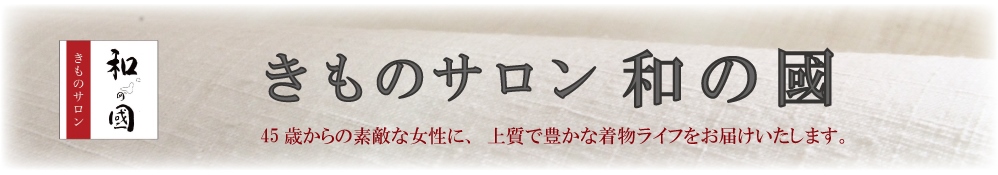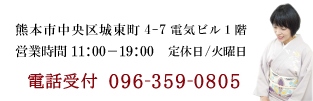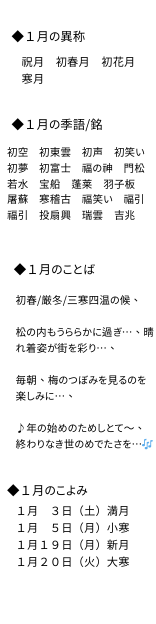99歳まで謡が出きる会でありたいとの思いが詰まった「白謡会」の秋の会が、明日「横浜能楽堂」で行われる。その会に参加させてもらう為午前9時発のANAで上京した。それに加え、もっと学び何かを吸収したい気持ちでいっぱいだ。そこで、夕刻までの時間に新国立美術館で開催されている「没後120年、ゴッホ展 ~こうして私はゴッホになった~」の企画特別展を見に行った。ゴッホが弟さんに仕送りをしてもらいながら実直にいきている姿、ミレーの作品に心動かし、「学ぶ」の語源である「真似る」ことから始めたその実践力に魅了されていった。肖像画と言えば、佐伯祐三の若かりし頃のものが印象に残っているが、ゴッホの肖像画にくぎ付けとなった。十数分経っただろうか。その絵と対峙するうちにその絵が何故か観音様に見えてきた。今まで全く味わったことのない不思議な感覚だ。「100年後まで、輝く肖像画を残したい」という思いが伝わってきた。 また、もう一枚印象に残った絵があった。ゴーギャンのと生活はトラブルが続き、わずか半年で終焉を迎えた。その間ゴーギャンを心酔していたゴッホが「ゴーギャンの絵」という肖像画を書いた。ゴーギャン専用の豪華な椅子で、ゴーギャンを椅子に見立てての肖像画。彩色もゴーギャン風。その椅子の上に燭台が置かれている。イヤホンガイドの説明では、「燭台が椅子の上に置いてあるので、夜書いた絵と思われます」とのことだった。私は夜の絵には全く見えない。脳がぐるぐると動き出し自分自身の価値観を探しだしている。数年前、「出光美術館」(東京・丸の内)にて仙崖和尚の展覧会の中で、「自画像とみられます」の時以来の変な感覚だ。ふと、その燭台はゴッホがゴーギャンを心酔しているがゆえの心の灯であったことに気づくと、その絵も一層輝きを増していた。来春早々には九州国立博物館で巡回展がある。もう一度対峙したいものだ。 たっぷりと身体全体に栄養をもらい、特別に稽古を付けてもらうために横浜へと向かった。新潟組(六日町)と熊本組が集い、本番さながらの稽古となった。平戸仁英先生の指導にも熱が入る。夜は自宅にお招きを受け前夜祭となった。師匠の心がいっぱい詰まった手作りのお料理も美味しい。新潟のお酒も進む。笑いも絶えない。桜木町のホテルに戻り、この秋初めて袖を通した「みさやま紬」(長野県・横山俊一郎氏作)の栗で染めた縞の着物をハンガーにかけると、バタンQだった。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】