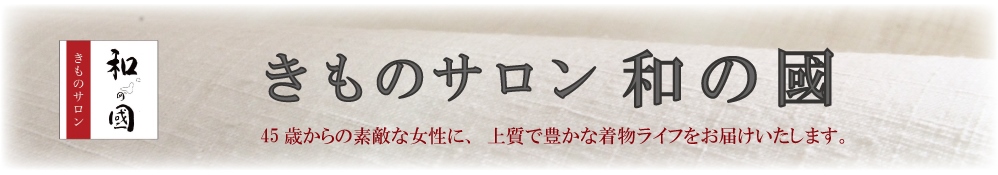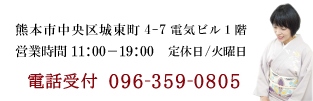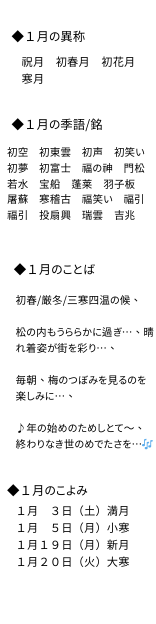今日は、いよいよ横浜能楽堂での発表会だ。お仕舞も出来はしないのに、心躍らせながらしながら単衣の黒紋付に仙台平の袴を履き、漆黒の紗羽織を着てホテルを出た。そこから能楽堂までは歩いていける範囲だ。9時前会場入りとなる。私は早着替えているので早速舞台に立ち「高砂」を舞ってみた。拍子を踏むとその踏み返りが何とも言えない。まさに「ひのき舞台」。急に上手くなった気がした。さて9時半から本番が始まった。私は見所(けんじょ)にいてもいいのだが、他の人のお仕舞を見る以外は、謡を聞きながら、舞台の横にある「鏡の間」で稽古を重ねた。武蔵の朝鍛夕錬には及ばないが、身体で覚えるのが一番。数がやがて形を生むからだ。午後1時半頃舞台に立った。緊張はあるものの私なりに気持ち良く舞えた。地謡の先生方が私の舞に合わせて謡をゆっくりめにしてくださる。その呼吸もまた有り難い。また、本番後も「鏡の間」に立って復習を繰り返しやってみた。当たり前の事だが舞台となると一発勝負なので、反省点がたくさんでてくる。しかしながら、3年目にしてやっと「仕舞が楽しい」と感じることができた。数日前来熊の折に、平戸仁英先生も「やっと仕舞いの型つけが言えるようになった」と笑顔でおっしゃっくださったことが、やけに嬉しい。「八島」の時もそうであったが、師の心はとてつもなく広い。 その後、私のお役はもう一つ、「田村」のシテ謡だ(シテ語より、クセまで)。こちらは、十年以上前から謡いこんでいる曲なので自分なりの色を付けることができる。思い起こせは、十年以上前菊池の自宅で週に一度、故・本山國廣氏を中心に、謡の基礎をみっちりと教えてもらっていたからだ。その方なくして今の謡はない。「あーたが、いつ辞めるて言うか心配しよったたい」と、故人の言葉が蘇ってきた。「きもの宣言」後興味が出てきた能楽の世界、「もし」ということがるならば、「もし着物をきなかったなら…。」「もし本山さんに出会わなかったら…。」この世界に魅了されることもなく、ましてや、リズムも取れず野球部で鍛え上げた大声を張り上げるだけの感じで、自他共に認める下手クソだったので、途中でとん挫していたことは明白だ。一人の師との出会いが、謡いを好きにさせてくれた。 それから、この曲には違う思い出も詰まっている。六帳目裏に、シテとワキ歌いの「春宵一刻。値千金。花に清香。月に影」とある。中国の故事からきており、聞かせどころだ。何十回、何百回謡っただろうか。お稽古を重ねていたときに、突然この文字が3D映像のように浮びあがってきた。「宝石箱みたいな珠玉の言葉の数々を謡っていた。俺は今までただ棒読みし声を張り上げているだけだった。」・・・と。 まさにカウンターパンチをくらったような出来事から早十年、おかげ様で自分なりに背景を思い浮かべながら謡うことができた。 終焉は午後七時近く、その後近くの居酒屋で打ち上げとなった。まさに、「汲めども尽きず、飲めども変わらぬ、秋の夜の杯」。私以外は、会終了後お着替えされ全てお洋服姿、着物姿は私だけ。おのずと着物談義にもなり、お声もかけて頂く。これも「着物パワー」なるものか・・・。様々なご縁、出会いを頂き本当に有難い。いろんな方にお世話になり、いろんな方々に可愛がっていただき今がある。いつの日か、恩返しができる人間になりたいものだと、強く心に誓った。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】