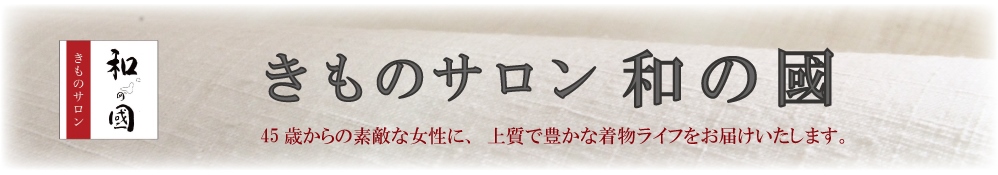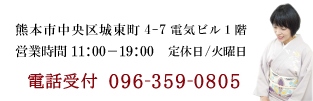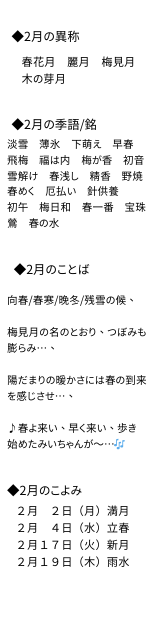午前7時30分、熊本市龍田町に住む弟より電話があった。「熊日に火の国染めの記事が大きく出てるよ」とのこと。丁度、用を済まし作務衣に半纏姿で車から降りようとしていたので、心急ぎ近くのコンビにに買いにいった。パラパラと17面をめくった。写真も大きく載り、作品ができた経緯が、分かりやすく流れるように書かれている。取材記事は、僕の意図と違う光の当て方で書かれることがたまにあるが、本当にお見事だ。記者の峰松清子氏に僕の思いが伝わった。2倍の喜びとなる。企画立案から約10年の歳月、喜びもひとしお。本業をやり遂げること、一つの事を諦めずにやり続ける喜びが、寒空の中、じんわりと体の中に入ってきた。 コンサートも一週間をきった。その今回、様々な「あわせ」があるので、ソリストとの連絡がとても必要。様々な要望もある。1回目、2回目、そして今年で3回目と、さらにやることが増えてくる。自分で企画し、専従スタッフもいないので、ここは僕が乗り越えなければならないところ。がさつな言い回しだが、ふと「やっつける」と言う言葉が頭をよぎった。「とにかく目の前のことを、やっつけていく。」これが一番の近道だろう。パンフレットも上がり、校正に入る。赤が入る。レッスン場を訪ねソリストの歌声を聴くときのみ、心が癒される。 そんな中、「忙中閑あり」を求めて、午前中お茶のお稽古に出かけた。昨年末同じ社中の中原様(仮称)と先生にウール(単衣仕立)の着物をお作り頂いた。中原様は、昨日の新年会で「明日その着物を着る」と聞く。チョッと寒いと感じたが、それなら僕が紬の袷を着ていくと失礼になる。よって、グレーの縞のウールに結城紬のヤシラミ織の帯を締め、その上に青森で求めた「裂織」の袖なし羽織を着て出かけた。「寒いから」とのことで中原様は紬の袷と変更となったが、僕の着る着物が前日に決まっていたのは有難い。でもチト風邪を引きそうだ。
本物志向のお客様に愛され続けて109年。「美しい訪問着」や「憧れの結城紬」などの手仕事着物を守りたいと考えています。店主(着物923)、ゆり女将共々、いろんなシーンで着物を愛用中。着物や着付けのことに加え、TPO・コーデ・お手入れなど安心しておまかせできる着物専門店です。
MENU
【和の國ブログ】